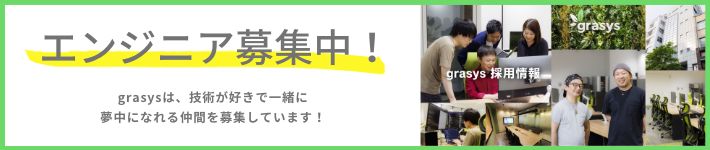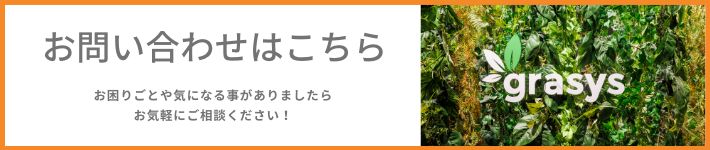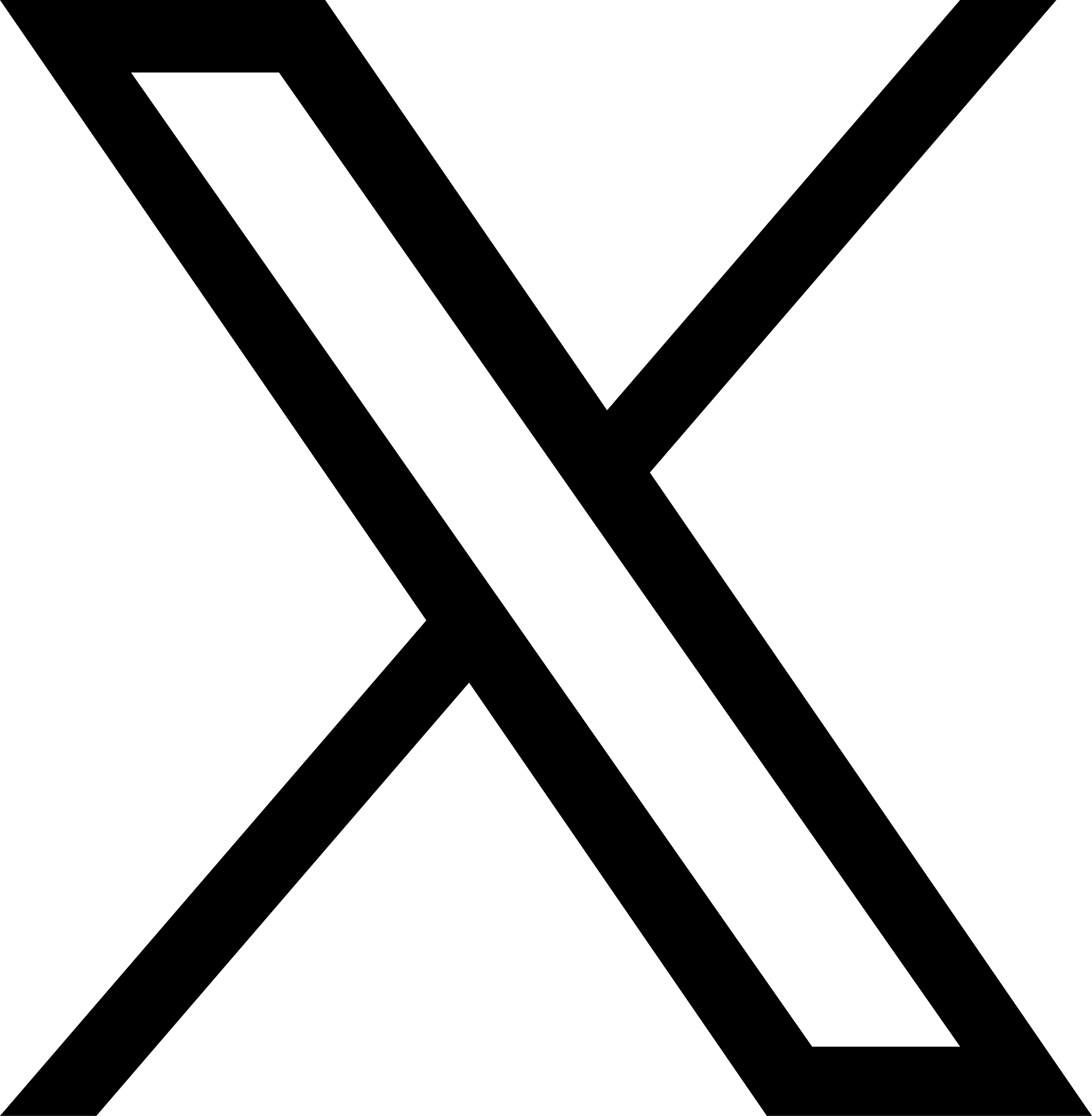目次
こんにちは、神庭です。
前回は、「生成AIの登場によって考えたこと。~指示力・確認力~」ということで、生成AIを使う上で必要な要素になると考えている指示力と確認力について書かせて頂きました。
今回は、確認力を深掘りしていきたいと思います。
確認力といっても、一例として自分自身で何度もチェックするとか、言語能力を向上させるとか、色々な要素があると思いますが、個人的には「専門性」と「批判的思考力(クリティカル・シンキング)」の2点がより重要と考えておりますので、この2点について書いていきたいと思います。
専門性
質問した内容が、専門的なものであれば、確認するにあたっては当然ながら質問内容についての専門性が必要です。
「自分で質問しているのだから、その分野の専門性をもっているなんて当然なのでは?」と思う人もいるかもしれません。
ただ、仮に知識が曖昧なまま、あるいは経験が不十分なまま、質問した場合でも、生成AIはそれっぽい回答をしてくれるため、しっかりとした確認をせずに、それっぽく使えているつもりになってしまう懸念もあると考えています。
1つ例を挙げてみます。
テスト的に、生成AIに請求書を添付して、会計の仕訳例を聞いてみました。
すると、貸借が一致しない仕訳例が出てきました。
そこで、私が貸借が一致していないことを指摘すると、貸借が修正されました。
ただ、勘定科目も誤っていたので、なぜそのようにしたのかを質問してみました。
すると今度は、「こういう原則に沿った会計処理です」というそれっぽい理由をつけて、回答の修正はありませんでした(※私が質問しただけであり、具体的な指摘をしたわけではなかったからかもしれません)。
なので、私は、生成AIの出してきた理由について指摘し、具体的に「こうすべきではないでしょうか?」と伝えました。
すると、今度は修正されました。
この後、更にもう1点、消費税の観点でも違いを指摘をし、修正がされました。
全部で3点の指摘をすることになりました(生成AIが「貴重なご指摘をありがとうございます」と言ってきました笑)
会計に少しでも携わっている人であれば、貸借が一致してない回答については、間違いをすぐに発見できると思います。
ただ、勘定科目については、生成AIも会計用語を使いながら正しい処理だと回答してきたので、質問している内容についての専門性が無い人の場合、「そうやって処理するものなのかぁ」と誤った理解をしてしまうかもしれません。
また、消費税の観点については見過ごしてしまうかもしれません。
実際に使ってみて、専門分野とは違う内容について使う場合には、注意が必要だなと感じました。
とはいえ、仮に専門性が無くても、批判的思考力(クリティカル・シンキング)があれば、誤った理解は防げるとも考えています。
批判的思考力(クリティカル・シンキング)
例えば、インターネットで検索するときに、全てを鵜呑みしているわけではないですよね?
「書いてある内容は本当なのか?」と思いながら見ているのではないでしょうか。例えば、サイト元がどういう会社なのか、あるいはどういう人が書いたものなのか、ということを1つの判断材料にしているのではないでしょうか。
中には「この人が言うなら間違いない!」と思いたくなるようなものもあるかもしれませんが、自分の都合の良い内容を見つけたからといって、それ1つだけで決めてしまうのもリスクがありますよね。
法律のような決まっているルールの話でいえば、e-Govで条文が出てくるので、その条文自体に間違いはないと捉えることはできますが、条文を読んでもわかりづらい内容の時には、複数の法律事務所のサイトから条文の解釈を参考にしたり、判例を調べたり等、複数の調査が必要であると考えています。
仮に、今調べている内容について、答えと思われるような内容が見つかった時にでも、例えば「過去と現在で、何か前提条件に違いはないだろうか?」と考えて、更なる調査をすることは重要ですよね。
生成AIが答えてくるということは、インターネット上に、生成AIが回答してきた内容に近い記載があるのだと思いますが、合っている保証はないですよね。むしろ、サイト元がわからない分、判断材料が無くなっていると言えるかもしれません。
そもそも、生成AIはいつの時点の情報を基に回答しているのかもわからないですよね(もちろん、人間に質問する場合でも、話している相手が、いつ時点のどこまでの知識・情報を持っているかにもよるのですが..)。尚、これは極端な例になりますが、所謂AI法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律案)が可決された日に、生成AIに「AI法案は可決しましたか?」と聞いてみた所、日本のAI法案は審議中であるという内容が返ってきました。
このように考えると、そもそも生成AIが出す回答は本当なのか?と批判的に考え、生成AIが出す回答は間違っているかもしれない、というスタンスで使う方が安全ではないでしょうか。
また、生成AIを使ってみることで、私たち人間だからこそできることも改めて見えてくるような気もしてきます。今後は、そのような内容も書いていけたらと考えています。
生成AIの登場によって考えたことについて他の記事も書いているので、よろしければこちらもご覧ください!
『生成AIの登場によって考えたこと。』シリーズ一覧